|
J.ゲール、北原理雄訳『屋外空間の生活とデザイン』
|
|
第二部、計画の前提条件
|
計画の前提条件
1.プロセスとプロジェクト
様々なコミュニティ活動が上辺だけのものでなくなるには、共通の背景、共通の関心、共通の問題など、ある種の公分母が必要。
↓
各地で、貴重なコミュニティの輪が物的な境界を「越えて」生まれている。
・大きな共通の問題を抱えた街では、強いコミュニティ感覚が街路や広場を越えて育つ。
それぞれの地区に具わっている前提条件を読み取り、その地区の住民各層の関心と要求を考慮すれば、どのような状況の下でも、公共空間における社会活動とふれあいのプロセスの間に、幾つかの段階の相互作用を観察することができるだろう。
❽これまで、社会活動とふれあいのプロセスと、住宅地プロジェクトのあいだに安定した相互作用をつくろうとする試みが各地でされて来た。
デンマークのコープ住宅団地(1978年)では、住宅群は15と前後の住戸を含む6つのグループに分けられ、各グループに共用室が設けられた(民主的プロセスを上手く機能させるためには、小区分やグループをつくる必要がある)。
さらに中央には、団地全体を対象にする大きなコミュニティ・センターがある。
住戸、住戸群、住宅団地、都市、という段階構成は、ここの住宅グループと団地全体の双方で、コミュニティと民主的プロセスを強化しようとする願いから生み出されたものである。
↓
物的構造が、住民が求める社会構造を反映し、それを維持している。
共用空間の段階構成は、社会的なグループ分けの段階構成を反映。家族には居間があり、住宅はふたつの共用空間(屋外の広場と屋内の共用室)を囲んで配列されている。そして最後に、住宅郡全体が団地の中央街路に沿って並び、そのなかに大きなコミュニティ・センターが置かれている。
家族は居間で顔を合わせ、住戸グループの住民は広場で顔を合わせる。団地全体の住民は、中央街路で顔を合わせる。
❽この種の団地プロジェクトの根底にある思想は、物的構造、すなわちプロジェクトが、視覚面でも機能面でも、住宅地の望ましい社会構造を支える働きをするというものである。
1.プロセスとプロジェクト
様々なコミュニティ活動が上辺だけのものでなくなるには、共通の背景、共通の関心、共通の問題など、ある種の公分母が必要。
↓
各地で、貴重なコミュニティの輪が物的な境界を「越えて」生まれている。
・大きな共通の問題を抱えた街では、強いコミュニティ感覚が街路や広場を越えて育つ。
それぞれの地区に具わっている前提条件を読み取り、その地区の住民各層の関心と要求を考慮すれば、どのような状況の下でも、公共空間における社会活動とふれあいのプロセスの間に、幾つかの段階の相互作用を観察することができるだろう。
❽これまで、社会活動とふれあいのプロセスと、住宅地プロジェクトのあいだに安定した相互作用をつくろうとする試みが各地でされて来た。
デンマークのコープ住宅団地(1978年)では、住宅群は15と前後の住戸を含む6つのグループに分けられ、各グループに共用室が設けられた(民主的プロセスを上手く機能させるためには、小区分やグループをつくる必要がある)。
さらに中央には、団地全体を対象にする大きなコミュニティ・センターがある。
住戸、住戸群、住宅団地、都市、という段階構成は、ここの住宅グループと団地全体の双方で、コミュニティと民主的プロセスを強化しようとする願いから生み出されたものである。
↓
物的構造が、住民が求める社会構造を反映し、それを維持している。
共用空間の段階構成は、社会的なグループ分けの段階構成を反映。家族には居間があり、住宅はふたつの共用空間(屋外の広場と屋内の共用室)を囲んで配列されている。そして最後に、住宅郡全体が団地の中央街路に沿って並び、そのなかに大きなコミュニティ・センターが置かれている。
家族は居間で顔を合わせ、住戸グループの住民は広場で顔を合わせる。団地全体の住民は、中央街路で顔を合わせる。
❽この種の団地プロジェクトの根底にある思想は、物的構造、すなわちプロジェクトが、視覚面でも機能面でも、住宅地の望ましい社会構造を支える働きをするというものである。
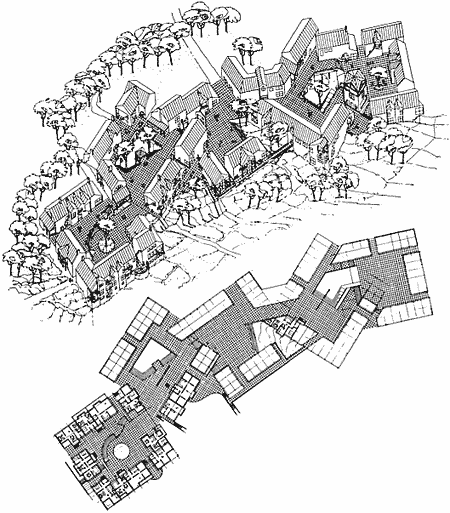
↑デンマークのスカーデ団地(1985年)
散漫な構造−郊外型の一戸建て住宅地、高層の住宅団地など
・これらの地域では、家族または世帯が社会構造の最小単位を成しているが、この単位の次に来るのは、都心やショッピングセンターなど、それよりはるかに大きな単位であり、両者の間の段階構成は極めて不明瞭。
・物的にはっきりした区分を持たず、個々の住戸がどこに「属している」のか、また住宅地がどこで「終わる」のか、はっきりしていない。
・住宅地の街路の設計は、コミュニティ活動をどこでどのように行なうのか、という点を視野に入れずに行なわれている。
ⓣ
不明瞭な物的構造そのものが、建物の間のアクティビティにとって明らかな障害物となる。
❽住環境を形成する上で、社会構造と物的構造の考え方が大切。また、公共空間と建物の間のアクティビティを、社会プロセスとグループの規模に関連させて考えなければならない。
・これらの地域では、家族または世帯が社会構造の最小単位を成しているが、この単位の次に来るのは、都心やショッピングセンターなど、それよりはるかに大きな単位であり、両者の間の段階構成は極めて不明瞭。
・物的にはっきりした区分を持たず、個々の住戸がどこに「属している」のか、また住宅地がどこで「終わる」のか、はっきりしていない。
・住宅地の街路の設計は、コミュニティ活動をどこでどのように行なうのか、という点を視野に入れずに行なわれている。
ⓣ
不明瞭な物的構造そのものが、建物の間のアクティビティにとって明らかな障害物となる。
❽住環境を形成する上で、社会構造と物的構造の考え方が大切。また、公共空間と建物の間のアクティビティを、社会プロセスとグループの規模に関連させて考えなければならない。
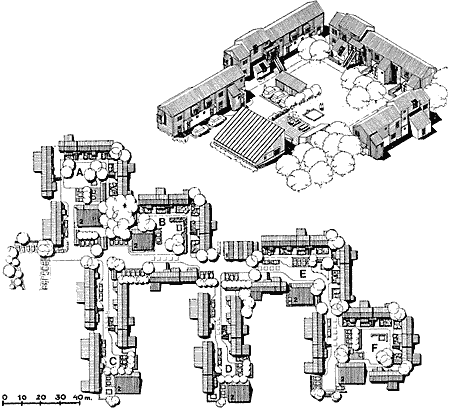
↑コペンハーゲンのティンゴーエン団地
プライバシーの度合い
居間から市役所広場まで、コミュニティ空間に段階構成を導入し、それらの空間を様々な社会グループと結び付けると、それぞれの空間にはそれぞれ異なる公私の度合いが生じる。
私的な屋外空間:庭・バルコニーなど
半公的な屋外空間:一群の住宅に囲まれた公共空間
より公的な屋外空間:地区の共用空間
完全に公的な屋外空間:市役所前の広場など
領域、安心、帰属感
色々な段階のコミュニティ空間を使い、社会構造とそれに対応する物的構造をしっかり築き上げると、小さなグループから大きなグループに、小さな空間から大きな空間に、私的な空間から公的な空間に、段階的に移行することが可能になり、大きな安心感と、私的な住まいを取り巻く領域への強い帰属感が得られる。住環境が現実の住まいを大きく越えて広がるようになる。
ⓣ
公共空間の利用を拡大
(例えば、親達はそうでない場合に比べてずっと幼い頃から、子供を屋外で遊ばせるようになるだろう)
屋外空間が自分の住まいの領域に属していると実感されれば、この公共空間とそのまわりの住宅を、それだけ気をつけて見守り、力を合わせて責任を持つようになる。公共空間が住環境の一部になり、人々は、住まいを大切にするのと同じように、破壊行為や犯罪から公共空間を守るだろう。
❽住宅地を、境界のはっきりした小さな構成単位に区分し、総合的な段階構成の一環に組み込むことが大切。
移行ゾーン−穏やかな移行
都市の街路と住戸グループとの間の移行を物的に表示するのは好ましいことであり、多くの場合、重要な意味を持っている。しかし、それと同時に、表示が厳しすぎる分離を招き、外界とのふれあいを妨げることがないように配慮する必要がある(視覚的な結びつきを十分に確保するなど)。
❽社会構造、物的構造、移行ゾーンは、はっきり区分されていると同時に近付きやすく、足を踏み入れ易いことが望ましい。
ex)バイカー団地(英)
それぞれの住戸グループを明瞭に区分するために、門と木戸を使って移行ゾーンが物的にはっきり区画された。しかし、その境界は、互いの交流が困難になるほど堅苦しいものではない。
2.感覚、コミュニケーション、規模
感覚−計画に必要な考慮
屋外空間と建物は位置をデザインする上で、人間の感覚がどのように作用し、どのような広がりを持っているのかを熟知していることが必要である。
正面性と水平性を持つ感覚器官
人間の体は、もともと時速約5Ɠの速さで水平方向に移動するのに適しており、感覚器感は、この条件に合わせてつくられている。(水平方向の視野は垂直方向に比べてはるかに広い)
↓
歩行者は事実上、建物の一階の床と、舗装と、街路空間のなかで起こっていることしか見ていない。
↓
出来事が知覚されるためには、それを観察者の前方のほぼ同じ高さで行なう必要がある(このことは、劇場等の観客空間のデザインに反映されている)。
距離
約30m以内の距離から、たまにしか会わない人でも見分けられるようになる。
20〜25mまで近づくと、他人の感情と気分を比較的はっきり読み取れる。
(社会関係の面で出会いが興味深く意味を持つのは、この距離からである)
(感情の伝達がなにより大切な劇(劇場)の舞台と一番遠い席との距離は、最大30〜35mである)
人間のコミュニケーションには、感覚に与える印象の強さと距離の相互作用が、広く利用されている。色々な社交場面の親密さと集中度を調整するのにも、個々の会話の始まりと終わりを制御するのにも利用されている。
↓
会話をするには、一定の空間が必要
・たとえば、エレベーター内や、奥行きが1mしかない前庭では、正常な会話はほとんど成立しない。それは、気の進まないふれあいを避け、好ましくない場面から身を引く方法がないからである。
・また、前庭の奥行きが深すぎると、会話のきっかけが生まれない。
↓
オーストラリア、カナダ、デンマークの調査によると、最適距離は3.25mである
社会距離
エドワード・ホール『かくれた次元』による数種類の社会距離の定義
・密接距離(0〜45cm) :優しさ、慰め、愛情、激しい怒り、強い感情が表現される距離。
・個体距離(0.45〜1.30m):親しい友人や家族の間の会話距離。食卓。
・社会距離(1.30〜3.75m):友人、知人、隣人、同僚などの間の日常会話距離。
応接セットには、この社会距離が物的に表現されている。
・公共距離(3.75m以上) :堅苦しい場面。一方通行の授業。
出来事を見聞きしたいが、巻き込まれたくないときの距離。
建築規模とふれあいの場における距離と強さ、親密さと暖かさの関係
・控えめな規模、狭い街路、小さな空間を持つ街や住宅地では、建物、建物の細部、空間を動き回っている人達をより強く体験することができる。こうした街は、親しみ易く、暖かく、身近なものと感じられ易い。
・大きな空間、広い街路、高い建物の街や住宅団地は、冷たく縁遠いものに感じられ易い。
車都市の尺度と人間都市の尺度
高速移動中にものを見分けるという目的によって、車都市は人間都市とまったく異なる尺度と規模を持つことになる。
ⓞ
意味のある社会活動、鮮やかな体験、会話が行なわれるのは、いずれも、人々が立ち止まり、座り、横になり、歩いているときである(「徒歩」の重要性)。
孤立とふれあいを左右する物的条件
居間から市役所広場まで、コミュニティ空間に段階構成を導入し、それらの空間を様々な社会グループと結び付けると、それぞれの空間にはそれぞれ異なる公私の度合いが生じる。
私的な屋外空間:庭・バルコニーなど
半公的な屋外空間:一群の住宅に囲まれた公共空間
より公的な屋外空間:地区の共用空間
完全に公的な屋外空間:市役所前の広場など
領域、安心、帰属感
色々な段階のコミュニティ空間を使い、社会構造とそれに対応する物的構造をしっかり築き上げると、小さなグループから大きなグループに、小さな空間から大きな空間に、私的な空間から公的な空間に、段階的に移行することが可能になり、大きな安心感と、私的な住まいを取り巻く領域への強い帰属感が得られる。住環境が現実の住まいを大きく越えて広がるようになる。
ⓣ
公共空間の利用を拡大
(例えば、親達はそうでない場合に比べてずっと幼い頃から、子供を屋外で遊ばせるようになるだろう)
屋外空間が自分の住まいの領域に属していると実感されれば、この公共空間とそのまわりの住宅を、それだけ気をつけて見守り、力を合わせて責任を持つようになる。公共空間が住環境の一部になり、人々は、住まいを大切にするのと同じように、破壊行為や犯罪から公共空間を守るだろう。
❽住宅地を、境界のはっきりした小さな構成単位に区分し、総合的な段階構成の一環に組み込むことが大切。
移行ゾーン−穏やかな移行
都市の街路と住戸グループとの間の移行を物的に表示するのは好ましいことであり、多くの場合、重要な意味を持っている。しかし、それと同時に、表示が厳しすぎる分離を招き、外界とのふれあいを妨げることがないように配慮する必要がある(視覚的な結びつきを十分に確保するなど)。
❽社会構造、物的構造、移行ゾーンは、はっきり区分されていると同時に近付きやすく、足を踏み入れ易いことが望ましい。
ex)バイカー団地(英)
それぞれの住戸グループを明瞭に区分するために、門と木戸を使って移行ゾーンが物的にはっきり区画された。しかし、その境界は、互いの交流が困難になるほど堅苦しいものではない。
2.感覚、コミュニケーション、規模
感覚−計画に必要な考慮
屋外空間と建物は位置をデザインする上で、人間の感覚がどのように作用し、どのような広がりを持っているのかを熟知していることが必要である。
正面性と水平性を持つ感覚器官
人間の体は、もともと時速約5Ɠの速さで水平方向に移動するのに適しており、感覚器感は、この条件に合わせてつくられている。(水平方向の視野は垂直方向に比べてはるかに広い)
↓
歩行者は事実上、建物の一階の床と、舗装と、街路空間のなかで起こっていることしか見ていない。
↓
出来事が知覚されるためには、それを観察者の前方のほぼ同じ高さで行なう必要がある(このことは、劇場等の観客空間のデザインに反映されている)。
距離
約30m以内の距離から、たまにしか会わない人でも見分けられるようになる。
20〜25mまで近づくと、他人の感情と気分を比較的はっきり読み取れる。
(社会関係の面で出会いが興味深く意味を持つのは、この距離からである)
(感情の伝達がなにより大切な劇(劇場)の舞台と一番遠い席との距離は、最大30〜35mである)
人間のコミュニケーションには、感覚に与える印象の強さと距離の相互作用が、広く利用されている。色々な社交場面の親密さと集中度を調整するのにも、個々の会話の始まりと終わりを制御するのにも利用されている。
↓
会話をするには、一定の空間が必要
・たとえば、エレベーター内や、奥行きが1mしかない前庭では、正常な会話はほとんど成立しない。それは、気の進まないふれあいを避け、好ましくない場面から身を引く方法がないからである。
・また、前庭の奥行きが深すぎると、会話のきっかけが生まれない。
↓
オーストラリア、カナダ、デンマークの調査によると、最適距離は3.25mである
社会距離
エドワード・ホール『かくれた次元』による数種類の社会距離の定義
・密接距離(0〜45cm) :優しさ、慰め、愛情、激しい怒り、強い感情が表現される距離。
・個体距離(0.45〜1.30m):親しい友人や家族の間の会話距離。食卓。
・社会距離(1.30〜3.75m):友人、知人、隣人、同僚などの間の日常会話距離。
応接セットには、この社会距離が物的に表現されている。
・公共距離(3.75m以上) :堅苦しい場面。一方通行の授業。
出来事を見聞きしたいが、巻き込まれたくないときの距離。
建築規模とふれあいの場における距離と強さ、親密さと暖かさの関係
・控えめな規模、狭い街路、小さな空間を持つ街や住宅地では、建物、建物の細部、空間を動き回っている人達をより強く体験することができる。こうした街は、親しみ易く、暖かく、身近なものと感じられ易い。
・大きな空間、広い街路、高い建物の街や住宅団地は、冷たく縁遠いものに感じられ易い。
車都市の尺度と人間都市の尺度
高速移動中にものを見分けるという目的によって、車都市は人間都市とまったく異なる尺度と規模を持つことになる。
ⓞ
意味のある社会活動、鮮やかな体験、会話が行なわれるのは、いずれも、人々が立ち止まり、座り、横になり、歩いているときである(「徒歩」の重要性)。
孤立とふれあいを左右する物的条件
孤立
壁・塀
長い距離
高速
高低差
背を向けた位置
壁・塀
長い距離
高速
高低差
背を向けた位置
ふれあい
壁・塀の除去
身近い距離
低速
同じ高さ
向かい合った位置
壁・塀の除去
身近い距離
低速
同じ高さ
向かい合った位置
建物のあいだのアクティビティ−プロセス
自己増殖プロセス
建物のあいだのアクティビティは自己増殖プロセスへと至る潜在的可能性を持つ。誰かが何かを始めると、あるときは直接の参加、あるときは傍観というかたちで、別の人がそれに加わる。個々の人や出来事は、互いに影響と刺激を与え合う。このプロセスがいったん動きはじめると、全体の活動は、ほとんどの場合、それを構成する個々の活動の総計よりも大きく複雑なものになる。
↓
デンマークにおける一戸建て住宅地と長家地区の子供の活動の調査結果
・長家地区では、子供の「密度」が、延び広がった一戸建て住宅地の二倍であった。
・子供の数が二倍の地区では、遊びの活動水準が四倍になっていた。
ⓣ
何かが起こるから何かが起こり、そこからまた何かが起こる。
住宅団地でも多くの出来事が起こっているが、そこでは、人と出来事が時間的にも空間的に拡散し過ぎているのである。個々の活動が一緒になり、もっと大きく意味のある、人の心に訴えかけるものとなってゆく、連鎖がはじまる機会がほとんどないのである。
ⓣ
何も起こらないから何も起こらない。
↓
建物の間のアクティビティの減少
↓
屋外がひどく退屈なので、子供達は屋内でテレビを見るようになるだろう。眺めるものがないので、老人達はベンチに座ることをしなくなる。街路は無人地帯の性格を帯びてくる。生き生きとした公共空間が崩れさり、街路が次第に誰の関心も引かない場所に代わっていく。これは、街路に破壊行為と犯罪をはびこらせる有力な要因となる。犯罪や不安が一端問題になると、誰も街路に出ようとしなくなる。悪循環の出来上がりである。
❽建物のあいだのアクティビティは、出来事の数と持続時間の積で表される。
そして、重要なのは、人や出来事の数より、むしろ活動の持続時間である。
❽交通の速度が低ければ、それだけで、街路にアクティビティが生まれる。
移動の速さが時速60Ɠから6Ɠに落ちると、個々の人間が視野に留まる時間が10倍になるので、街路上の人の数も10倍に見える。
街路のアクティビティ、人と出来事の数、屋外で過ごす時間、この三者の間に見られる関係が、新旧の住宅地で建物の間のアクティビティの条件を改善する上での鍵である。
自己増殖プロセス
建物のあいだのアクティビティは自己増殖プロセスへと至る潜在的可能性を持つ。誰かが何かを始めると、あるときは直接の参加、あるときは傍観というかたちで、別の人がそれに加わる。個々の人や出来事は、互いに影響と刺激を与え合う。このプロセスがいったん動きはじめると、全体の活動は、ほとんどの場合、それを構成する個々の活動の総計よりも大きく複雑なものになる。
↓
デンマークにおける一戸建て住宅地と長家地区の子供の活動の調査結果
・長家地区では、子供の「密度」が、延び広がった一戸建て住宅地の二倍であった。
・子供の数が二倍の地区では、遊びの活動水準が四倍になっていた。
ⓣ
何かが起こるから何かが起こり、そこからまた何かが起こる。
住宅団地でも多くの出来事が起こっているが、そこでは、人と出来事が時間的にも空間的に拡散し過ぎているのである。個々の活動が一緒になり、もっと大きく意味のある、人の心に訴えかけるものとなってゆく、連鎖がはじまる機会がほとんどないのである。
ⓣ
何も起こらないから何も起こらない。
↓
建物の間のアクティビティの減少
↓
屋外がひどく退屈なので、子供達は屋内でテレビを見るようになるだろう。眺めるものがないので、老人達はベンチに座ることをしなくなる。街路は無人地帯の性格を帯びてくる。生き生きとした公共空間が崩れさり、街路が次第に誰の関心も引かない場所に代わっていく。これは、街路に破壊行為と犯罪をはびこらせる有力な要因となる。犯罪や不安が一端問題になると、誰も街路に出ようとしなくなる。悪循環の出来上がりである。
❽建物のあいだのアクティビティは、出来事の数と持続時間の積で表される。
そして、重要なのは、人や出来事の数より、むしろ活動の持続時間である。
❽交通の速度が低ければ、それだけで、街路にアクティビティが生まれる。
移動の速さが時速60Ɠから6Ɠに落ちると、個々の人間が視野に留まる時間が10倍になるので、街路上の人の数も10倍に見える。
街路のアクティビティ、人と出来事の数、屋外で過ごす時間、この三者の間に見られる関係が、新旧の住宅地で建物の間のアクティビティの条件を改善する上での鍵である。
