|
ノーバード・ショウナワー、三村浩史監訳
「世界のすまい6000年 2東洋の都市住居」、彰国社、1985年 |
|
日本
|
平安京は中国の洛陽や長安などの都城をモデルにしたが、その規模は面積にして長安の5分の1、南北4.95Km、東西4.206Kmであった。大陸のものとは違って、島国においては脅威となる外敵がなく、都城といっても、城壁も城門ももたない防備性の低い都市であった。
市街地は条坊制といって、格子状の街路網で区切られた数百の街区により構成された。貴族と共に彼らの需要に応じて、労役、加工、販売などに働く多数の庶民も平安京に定住したが、彼らはこの区画規模をさらに細分割して貧しく小さな住居を道にそって連担して建設した。街区の中央部つまり各住居の裏側は空地であって、共同の井戸と便所があり、また耕作や多目的な屋外生活に用いられた。
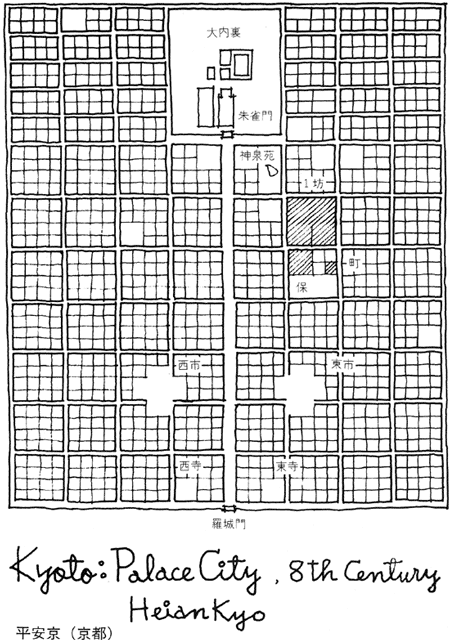
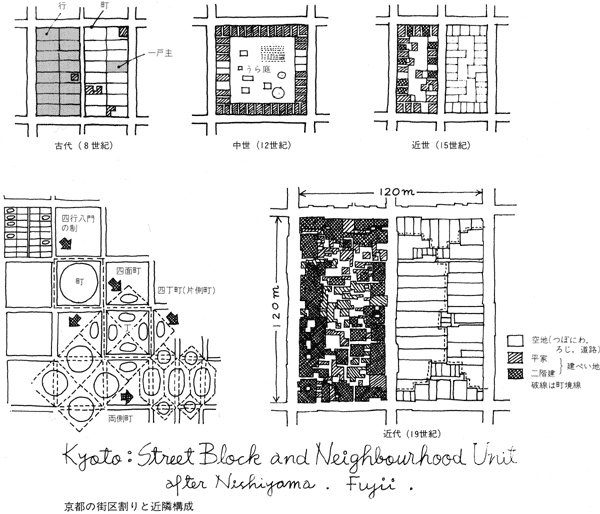
京都の町家
町家は商業自営者または生産職人とその家族や使用人が住む併用住宅であり、被支配階級である彼らは、制約された都市空間の配分のなかで高密度な居住を営まねばならなかった。町家に住むのは父系の世代家族であり、「家」という社会的信用単位の継承を第一に考えてきた。
町家の建築的特徴を規定しているのは、平安京以来の街区を受け継いでいることである。初期の平安京の近隣単位は、坊と呼ばれる街区ブロックごとの単位であった。それが商業が発展するにつれて、通りに接する間口の重要さが高まり、やがて通りの両側を一体とする町区単位へと変わった。従って現在では、一つの街区は四つの町内に属している。住居の拡張は、まず裏側に向けて進み、共同空地は次第に割拠されつつ消滅していった。120m角の正方形の街区が背割線で区切られると、おのおのの敷地の奥行きは最大で60mになる。なお、近世の都市改造で縦に2分割された街区の奥行は30m弱である。これに対して、個々の敷地の間口は狭く、5〜8mである(「うなぎの長家」と呼ばれる所以)。
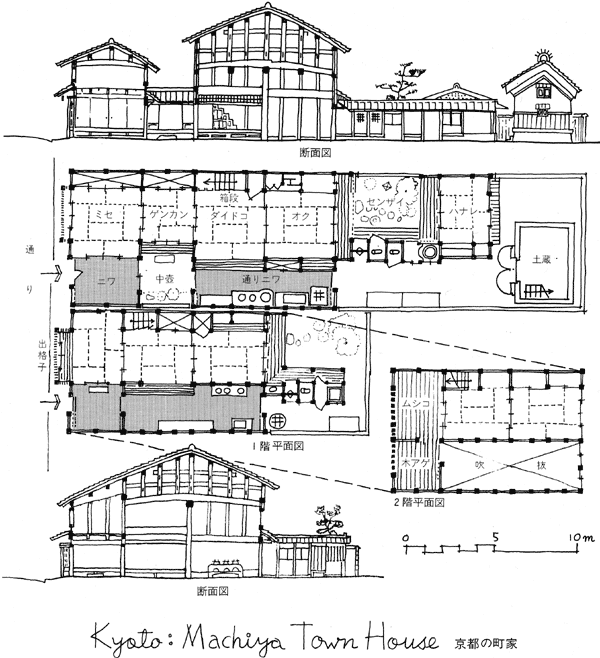
細長い敷地を合理的に利用し、高い居住性を獲得する上で、最も大切な役割を果たしているのは、店先・玄関から裏庭まで走っている通り庭である。通路であると同時に併用住宅として客との軽い応接、荷捌き、家事、室内環境の調節といった多目的の働きをしている。吹き抜けになっているので、カマドからの排煙(煙突はなく、煙は大屋根の小屋裏をいぶしつつ天窓から抜ける)と採光、広さの獲得と軸性の主張などの効果をもつ。中程から奥に日々の炊事のための小さなカマドや特別の行事の日のための大カマド、屋内井戸(盆地である京都は地下水位が浅い)、流しおよび食器棚などが並ぶ。
座敷(上図ではオク)とその先にあるセンザイと呼ばれる庭との間には縁側があり、外気と外光から室内の環境を和らげている。座敷のしつらえは季節によって変化する。冬に用いていた板戸、ふすま、明り障子は、夏には通気性のよいヨシの障子や御簾に換えられる。畳敷きの床もヨシを編んだ敷物に換えられる。通風をよくし、床の間の飾りを見た目に涼しげにし、庭に水をまいて夏の暑さをしのぐのである。
正面のファサードを見ると、2階は階高が低く抑えられている。身分の高い人の往来を見下ろしてはいけないという封建的規制と防護性とが加わったものであろう。内部は物置きや従業員の住み込み部屋に用いられる。内庭に面する裏側の部屋は家族用で、ふとんを用い、部屋の機能を昼と夜とで使い分けている。裏側の居室は大きな開口部を持ち、そこから庭と隣家、そしてその屋根越しに盆地を取り巻いている山並と空を眺めることができる。
坪庭やセンザイは高密な居住空間に安らぎをもたらす装置であるとともに、夏の耐え難く蒸し暑い住居に通風を促す垂直ダクトの役割を持っている。
店の間と通りとの間には堅固で精緻な造作の木格子が取り付けられている。防護的なものだが、通風が良く視覚的にも通りからは覗き込みにくく、内からは通りが良く見える。木格子は取り外せるので祭礼の日に店の間を通りに向けて飾り解放することができる。狭い道幅(6〜8m)と低く抑えられた2階屋がつくる街並は、人間的スケールを保っている。
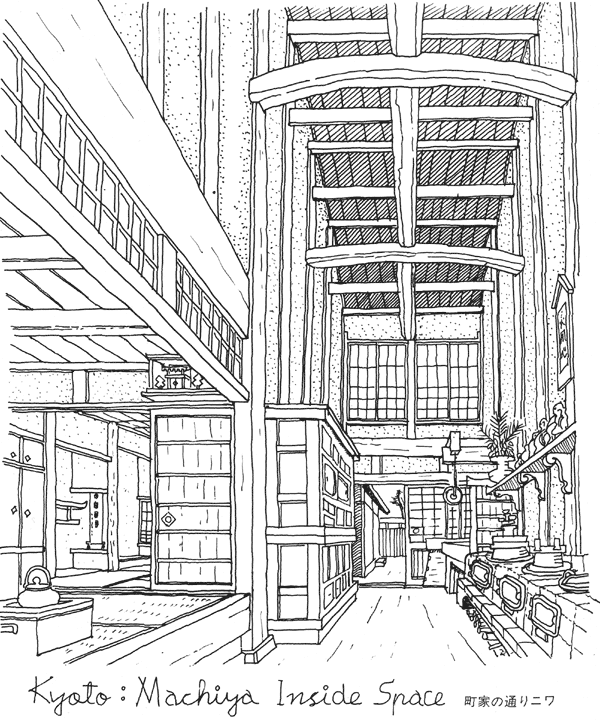
家屋の構造的な木組みの寸法体系は畳の寸法に合わせて標準化されている。京都の場合、畳一枚は94.5cm×189cmで、この畳の数で部屋の大きさも柱間の間隔も決定される内法制を採っている。このため、畳はもちろんのこと、建具そして箱階段に至るまで互換性があり、引越しのときは家財と共に運んで次の家屋にはめ込める。
屋根は家屋の連担を可能にする平入り大屋根形式である。いぶし銀色の上質の瓦が使用され、街並に重厚さをもたらしている。
東洋の都市住居の文脈のなかで、京都の町家を考えてみると、低層高密住宅であり、家屋が互いに連担していて私的な生活部分は中庭に向いており、表の通りに対しては防護的であるという点は、共通する特徴だと言える。その一方、モンスーン気候帯にあって降雨量が多いこと、夏に蒸し暑く通風が大切なこと、社会が平穏になり自衛の必要が少なくなったこと、商業併用住宅であって間口の制約が厳しいこと、主要な素材が木であること、などの理由から、大陸型の都市住宅とは異なった独自の様式の形成を見たのである。
