|
ノーバード・ショウナワー、三村浩史監訳
「世界のすまい6000年 1先都市時代の住居」、彰国社、1985年 |
|
恒久的な住居(Permanent Dwellings)
|
進歩し、安定した食糧生産が全労働時間の分化をもたらし、食糧生産に必要でない人は、各種労働に専門化できることになった。こうして、これまで述べて来た社会に比べて生活が複雑となり、社会がはるかに進歩した段階に達することとなった。
この段階になると、余剰食糧が人間以外の動力源を用い、複雑な道具を使って生産される。倉庫や分配施設もでき、遠い市場に生産物を運ぶ輸送組織も発達する。食糧生産の増大に加え、専門化した商品が製造され、流通するのに伴い血族関係に基礎をおく社会関係が弱まり、これにかわって職業を通したつながりが強化されていった。更には、進歩した農業社会では、作物や家畜に対する支配が増大していく結果、財産の概念が発展し、土地は明白に個人的に所有される財産となった。
この段階では、農民は土地を永続的に耕作する。輪作や休耕ないし土地を肥沃にすることを学び、個々の植物の世話よりも、むしろ土地の世話に注意を向ける。
発展がこの段階に達すると、社会が多くの要素に影響されるようになり、複雑な相互関係が形成される結果、単純なくわを用いる農夫の社会と比較すると、ずっと多くの住居形態が生じることになる。これらの形態の多くを完全に描写することは大変な仕事である。そこで、多くの恒久的な住居に共通して見られる特徴について一般的に述べ、同時に数例については詳細を描くことが必要とされる。
恒久的な住居は、すべて丈夫な建築材料で造られている。壁は木造か組積造である。住居が持続して使われ、各地で職業が専門化していった結果、職人の技量が向上し、扉や窓、屋根、床、煙突、巧妙なディテール等も入念に造られるようになった。室内環境も、快適さを考えてコントロールされるようになった。広さも一段と広くなり、普通、幾つもの部屋で構成される。
恒久的な住居には二つのタイプがある。一番目は、居住部分と納屋、馬屋、その他の付属的な建物より成っている。二番目のものは、一つの建物の中にあらゆる機能を含んでいる。しかしながら、この建物の中にある様々な場としての機能は、垂直、または水平の建物要素によって互いに分離することが可能である。
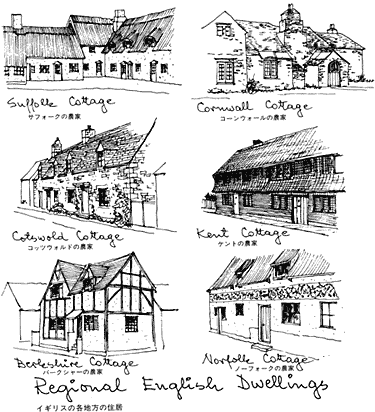
恒久的な住居は、主として温暖な地域で見られるため、壁は高い熱容量か、高い断熱性を持った材料で造られる。伝統的に、ある地域に特有な材料が建築物に使われるために変化に富む地域的特性に合致し、その地域に調和する多様な住居が造られることとなる。
材料本来の性質やその質感によって生じる特性は、気候風土に起因する要求と結合して独特なデザインを生むことになる。屋根の傾斜や軒の出、窓の大きさや形態などがそれである。
トゥル−ロとは、イタリア南部アプリア地方にあるムルジアの住民が住む伝統的な恒久建物である。この地方では、トゥルーロが原形になった住居が各地で見られる。
アプリアの田園地域では農業がいまだに主要な職業である。ぶどうとオリーブが主な作物で、小麦、豆、トマトなどの副次的作物がオリーブの木の間に植えられている。通常、畑は狭く、厚く乾燥した石の壁で囲まれている。土地は、多くの労働力を投下することによって初めて耕作に適するようになる。土地は石灰岩床の上が僅か数インチの有機質土壌に覆われているだけである。畑の準備には、最初に薄い表土を取り除き、その表土を一時的に保管しておく。それから、むき出しになった石灰岩を60cmの深さまで粉砕する。最も良い石は建物の建設用にためておき、残りは粒の粗いものは下に、細かいものは表面にという順序で戻しておく。ボロと呼ばれる赤土が近くのくぼ地から運ばれ、粒の粗い石灰岩の上に40〜50cmの厚さに突き固められる。最後に、ボロの上に保管しておいた表土が注意深く広げられる。
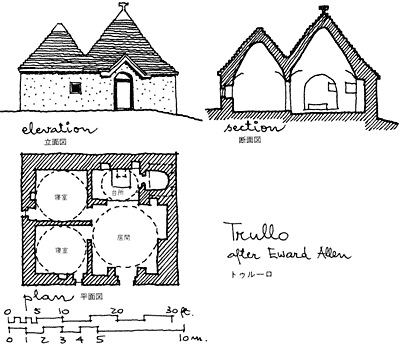
トゥルーロは主として畑からの石を用いて建設される。このほかに、住居の地下に大きな雨水の水ためやワインのたるを造る過程で切り出される石も使う。露出した岩床がトゥルーロの基礎として役立つ。
長方形の部屋は厚い石の壁に囲まれており、アルコーブやニッチのくぼんだ空間がつくられている。屋根は石のドームで、表面は平らな石で仕上げられている。壁には石灰の漆喰が塗られ、ドームの頂部も同じである。雨水は屋根から水ために集められる。
暖かい季節の間は、石で出来たトゥルーロは涼しくて快適である。冬にはトゥルーロは冷たくてじめじめする。そのため、昼間はドアを開け放して室内を乾燥させようとする。女性は玄関口の外側に座って、繕い物や編み物のような仕事をするが、つつましく家の方を向いて行う。
農家の敷地には複数のトゥルーロが建てられ、時には2ダースを数えることもある。干草の納屋は、大きく平らで取り外しができる石をかぶせた、円錐の頭部を切り取った形をした屋根をもつ。その屋根には、農夫が干草を積み込むときのために踏み段がつくられている。そして鶏小屋でさえ低く粗末なトゥルーロでつくられている。建物が互いに接して建てられているため、全体的に眺めると、建物から建物へと優美に屋根が続いているのが特徴である。
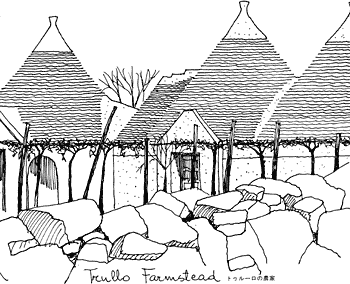
チェコスロバキア東部のスロバキア地方の農家は、農家の原形と考えられるもので、現在でもキスセやオラバなどの農業地域に多く見ることができる。
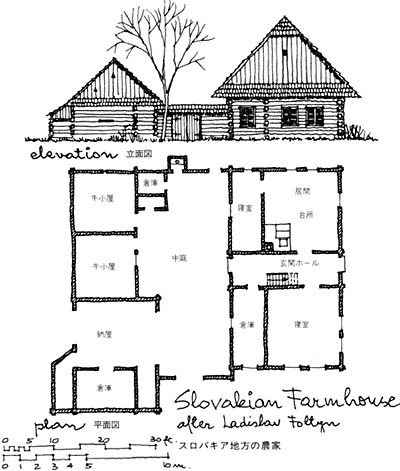
典型的な農家は、山にある豊富な松材を切り出した丸太で建設されている。一般に平家だが、斜面では一部が地表面上に出た地下室が必要になることもあり、そのときには下の階は倉庫か作業場、あるいは家畜小屋として使用される。基礎は野の石で造られ、隅が組み合わされた水平な丸太で出来た壁を支えている。すべての接合部には漆喰が塗られている。屋根は板葺きで、入母屋風になっている妻には羽目板がはめ込まれている。窓には漆喰で飾った枠組みがつけられ、簡素な彫り物や飾りが家の外観を引き立たせている。
入口は可能な限り南を向く。中庭の北側には母屋と平行に細長い建物があり、納屋や馬小屋、貯蔵室として使われている。屋根のついた塀と村の通りに面した大きな表玄関、そして背後にある家畜小屋、屋外便所などで庭は完全に囲まれている。
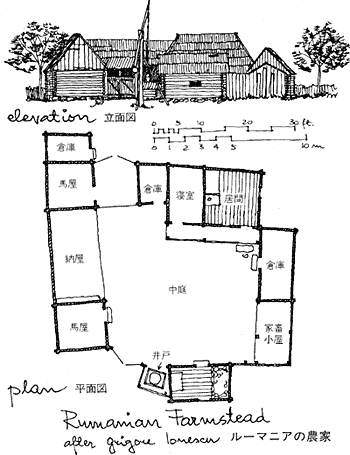
住居と馬小屋、そして他の付属的な建物で中庭が形成されることは、南東ヨーロッパの農家の特徴でもある。
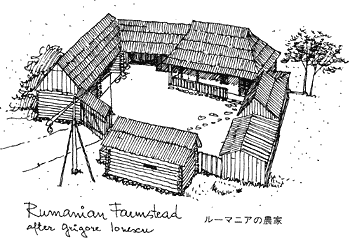
左に例示したルーマニアの農家はスロバキアのものと多くの類似点がある。すなわち、両方とも木材が豊富な山の多い地方であり、その結果、建築材料としては主に木材が用いられている。
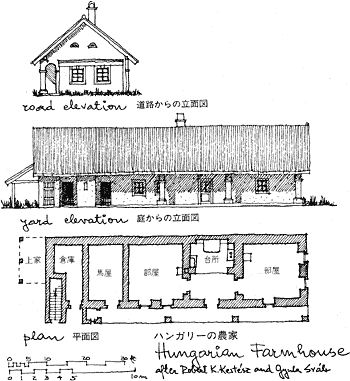
木材に恵まれないハンガリーでは、床と屋根、塀にしか木材は用いない。壁はもっぱら石などの組積造となっている。
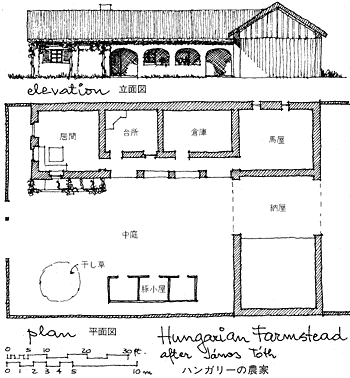
スイスの中央低地に昔からあるベルンの農家も、恒久的住居の例である。典型的な農家は数棟の建物から構成され、主屋を中心として周りを副次的な建物が取り囲んでいる。建物は、親が隠居したときに住むストックリやスパイヘルという名の立派に飾られた穀物倉、木の小屋、豚小屋、納屋、パン焼き小屋などがある。
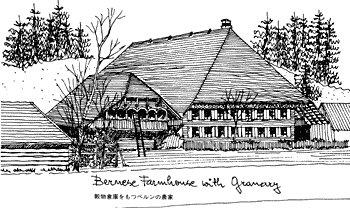
ベルンの農家で発揮されている職人の技量は非常に進んだものであり、美的な関心をそそるものである。
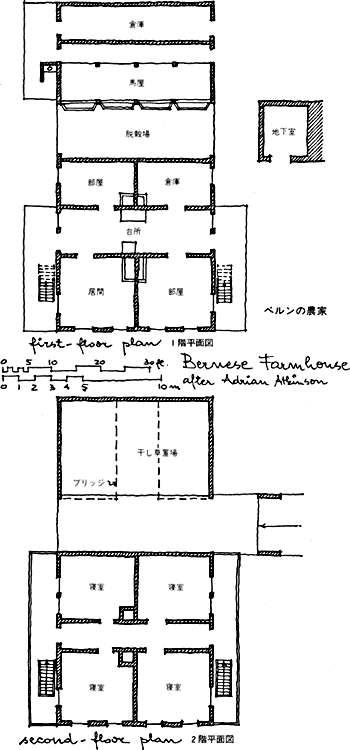
主屋は一つ屋根の下に、家族の住居や馬小屋、干し草置場(スロープから入る)、物置、脱穀場などをもっている。脱穀場は住居部分と馬小屋や干し草置場との中間に位置している。住居の1階には居間と寝室があり、妻壁に窓を持つ。その後ろには建物の幅いっぱいに大きな台所があり、奥に寝室と貯蔵部屋が続く。これらの空間の2階は寝室か貯蔵場所になっている。2階へは急な外階段を利用してバルコニーに上がる。
玄関を入ると大きな台所がある。そしてこの台所の両側に二つずつある部屋に出入りする。二つある部屋の各組には、入念に造られた陶器の炉が置かれており、台所から焚いて両方の部屋を暖める。
居間は静かな場所で、そこで家族が食事をし、主人が読書をし、女が糸を紡ぐ。部屋の一角には、壁を背にして造り付けの椅子を持った食卓が用意されている。食事時には、父親が食卓の上席を占め、息子はその右側に、妻と娘は左側に並ぶ。子供達は年齢順に座り、召使と女中は食卓の末席に座る。
食卓の上席に最も近い隅は「聖なるコーナー」とされており、十字架や聖家族の絵が置かれる場所である。
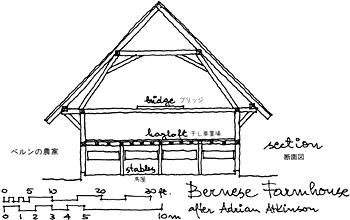
東アジアのモンスーン圏すなわち温帯多雨気候区にある農村で、最も基本的な定住様式といえば、水稲を主作物とする農業集落である。
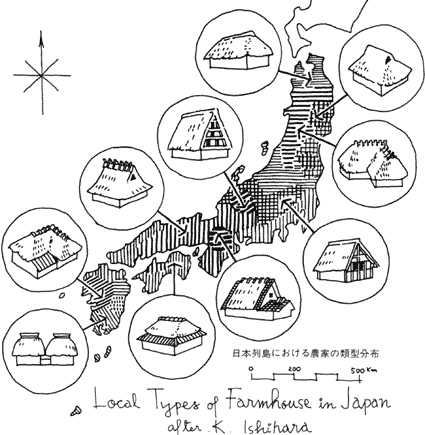
日本列島は、北は冷温帯から南は亜熱帯に至るまで、約3,000kmにわたって弧状に細長く連なっている。
本州島についてみると、平均的な降雨量は年間1,500mm、夏期は蒸し暑く、冬期は寒冷で、日本海岸は積雪が多い。水田は縁に畔を築き表土上の数cmに水を張る。
水源林、ため池、水路および用水は共同管理である。低地では、排水、洪水の防止のための河川の制御がことのほか重要である。水系としての用水の配分はしばしば集落間の争いの原因となってきた。
日本の農業集落は、水を媒介とする共同体であるといって良い。
集落の形態は地方によって異なり、散居村も塊村も街道村もある。一毛作米作地帯では1戸当りの耕地は概して大きく数haに及ぶことが多い。他方、二毛作が可能で米と商業作物との混合耕作地帯では、0.5〜1haである。家族についてみると子供の人数は、平均して5人程度だったが、現在では2〜3人に減っている。年をとった親との同居は一般的な居住形態であり、三世代の家族が多い。現在では家族人員は4〜8人の区分の中に大部分が分布している。
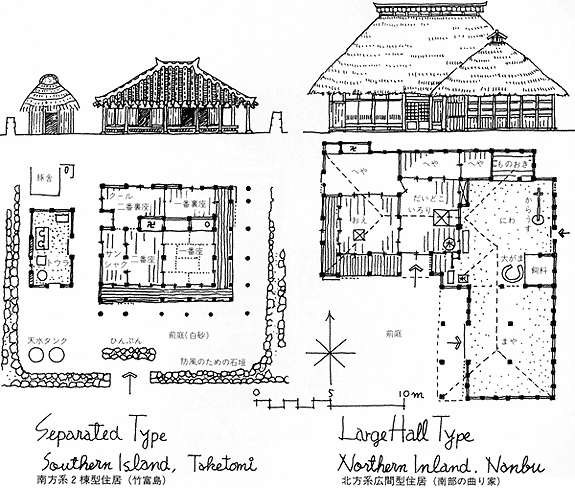
日本の農家の建築としての第一の特徴は、二つのレベルの床面の存在である。土間は、家事と屋内農事の立働きの場所である。土間は穀物を乾燥させたりするための南側の前庭や耕作に使う牛馬の小屋にも続いている。土間は、「三和土(たたき)」といって土に消石灰と苦汁(にがり)を混ぜて突き固めたもので、適度に湿っていてほこりを立てない。土間には炊事用のかまどがある。燃料はわらと薪であった。
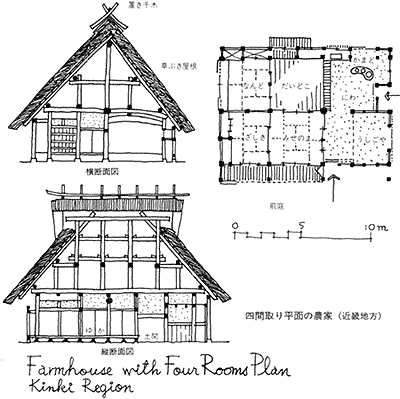
いま一つの床面は、土間から約50cm前後高くなっている板床張りの部分である。
床張り部分の平面は数多くの類型に分類されているが、最も定型化されたのは、「田」の字型の四間取り平面である。南側の庭に面して連続する二つの部屋は、「ザシキ」、「デ」などと呼ばれ、それぞれあらたまった客、日常の客の応対に用いる。「ザシキ」は格式あるスペースで、床の間というシンボリックな装飾棚、家の祖先を祀る仏壇を配し、床は畳を敷きつめている。「ザシキ」、「デ」は、武士階級の格式ある住居の様式を村の支配階層の農家が採用し、次第に中流農家にも広まったものである。
しかしながら、床張りの最も基本的な機能は、休息と就寝のためのもの
家事や団らんのスペースも、土座式では土間に設けた炉を中心としたものであったが、四間取りでは、「ダイドコ」という板張りの床に家族が座って食事をとる。床に敷物を敷いて座る。各自が小さな膳を用いることもあり、共同の食卓は用いない。
寒冷な地方では、土間にあった炉が、床張りの部分に移って「イロリ」とよばれている。ダイドコの中央に設けられる「イロリ」の火は、炊事だけでなく採暖や乾燥のための熱源になる。封建時代の家父長制の下では、この「イロリ」の周りの着座位置には、正客・家長・主婦などの厳格な序列があった
。寒冷地ではこの「ダイドコ」の生活様式の役割が大きく、他方「ザシキ」は未発達であったから、このタイプのプランを広間型と呼んでいる。四間取り型と並ぶ日本の農家の二大類型である。
温暖な地方では「イロリ」はなく、土間の「カマド」が炊事に用いられる。「イロリ」も「カマド」も煙突はなく、煙はそのまま屋根裏にのぼっていき、茅葺きの屋根材をいぶしてその耐久性を増しつつ排出される。「カマド」は家族の生活の安全を守る守護神が常住していると考えられる神聖な場所である。
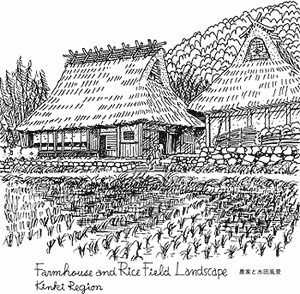
家屋の構造の特徴は、柱と梁による軸組構造と大きな茅葺きの屋根に見ることができる。杉や松という直線材の利用が容易であったこと、巧妙な仕口が発達したことから、複雑な軸組構造を普及させたのである。
軸組構造であることから、外壁・内壁共に少なくてすみ、開放性の室内が可能になった。間仕切りとしては、板戸、襖、障子が用いられたが、これらはいずれも引戸であって、取り外しが可能である。大勢の客を呼ぶような行事の場合、「ザシキ」と「デ」の間の建具を外すと大空間になるのである。室のプライバシーという点では頼りないものであるが、家父長制の家族では個々のメンバーの独立性は問題とされなかったことに留意しておこう。
屋根は大抵は茅葺きである。茅の入手が困難な地方では藁葺き・板葺きである。長い梅雨期に耐えるように屋根の勾配はきつく、その大屋根の形態が日本の農家のたたずまいを際立たせている。軒は、開口部と壁とを風雨から守るために大きくせり出している。この軒下のスペースは、強い日差しを防ぎ、室内と戸外との媒介空間としてのやすらぎをつくっている。最も単純な屋根の形は寄せ棟であるが、煙出しから発達したと思われる入母屋造りは、より洗練された美をもっている。建設工事にあたっては「ユイ」といって村人による相互扶助方式がとられてきた。
これらの木材・茅・基礎玉石・粘土などの建材は、山林と河川がこきざみに入り組み、どの地方でも採取しやすいという日本列島の地形条件をよく反映している。
第二次世界大戦後のに農地改革、家父長制の崩壊、都市化・工業化は、日本の農村を大きく変えた。ここで描いたような農家の原形を見つけることは次第に難しくなっている。現代日本の農家の多くでは、居住のための棟と農作業のための棟とは、はっきりと分離されることが多く、前者は都市の専用住宅の平面に近づいている。特に、土間は消えて、板張りのダイニングキッチンに変わった。コミュニティの集会施設が整ったのに、儀礼や行事の時の大勢の来客に備えて、自宅に広い「ザシキ」を保有する傾向は依然として強い。材料も工業化された新建材や他の地方や海外から輸入したものに頼るようになり、地元の自然材は殆ど使用されなくなった。
