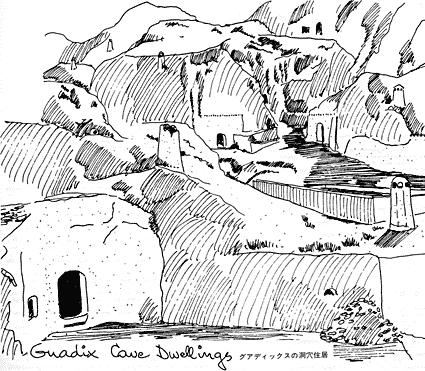|
ノーバード・ショウナワー、三村浩史監訳
「世界のすまい6000年 1先都市時代の住居」、彰国社、1985年 |
|
むすび(Conclusion)
|
今日でも、年代的にはシュメール文化に先立つ何千年前の石器時代の文化を直に見ることが可能である。つい最近も、石器時代の小集団の社会がフィリピンのタサディで発見された。この社会は過去に文明とは全く接触を持っていなかった。文明が移入されてきた結果、現存する石器時代の文化があまり遠くない将来にすべて消えてしまうだろうということは確かであるが、ほとんどの建築史家が、石器時代を遠い過去の神話化された時代として扱うのは道理にあわないことだと言えよう。
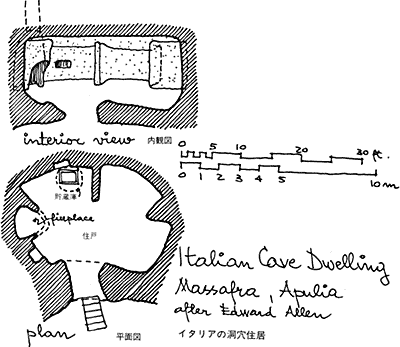
もちろん、幾つかの洞穴から、それが先史時代に人間に使用されていたという証拠が見つかっているということも否定することはできない。先史時代の人間が、一時的な住処としてしばしば洞穴を使ったり、さらには食物を求めての季節的な移動に際して洞穴を繰り返し使用したりしたことは、ありそうなことである。
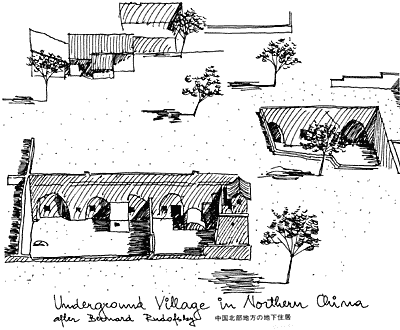
円形の平面は、建造物に一層洗練された長方形の形態を採用している社会においても見られることがある。しかしながら、こうした円形平面の存在は、原始時代の住居形態が残存しているものだと考えることができる。例えば、プエブロ・インディアンにとって神聖な場である伝統的なキバや、ドゴンの住居の円形の台所などがそれである。
円形の平面は二つの面で発展を制約されている。まず第一に、構造的に考えて、拡大することを制限される。建物の面積が増加すると、比例して直径が長くなり、梁を架けることが至難の業となる。これとは対照的に、長方形は幅を広くするのには制限があるが、長さの点では制限されない。円形平面の第二の制約は、次々に拡張や増築をしていくことの困難さである。一方、長方形や正方形では、建築材料的に考えても、効果的な空間利用という点から考えても、拡張を行うことはより容易であり、経済的でもある。従って、住居の発展について以下のことが言えよう。すなわち、住居の形はまず円形で始まり、次いで楕円形、それから角を丸めた細長い長方形、そして最後に角張った長方形や正方形へという一連の過程を通って発展してきていると見ることができる。
明らかに、建築物の構造も次第に複雑なものへと進歩してきている。ミツバチの巣のような最も簡単な住処は、屋根と壁を兼ねた覆いのシェルターで、両者の区別はない。次の段階になると、壁と屋根とが分化する。また、最も簡単な住居では、入口は窓と煙突を兼ねている。徐々に様々な機能が分化してゆく。事実「窓」(window)の語源をたどってみると、風(wind)と目(eye)であり、それは煙出しの穴と明り取りを結合した屋根の開口部を意味していた。
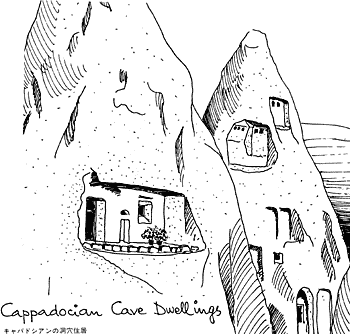
この一見すると矛盾しているように見える発展は、また社会経済的構造によるものだと考えられる。生存するための社会的、経済的な単位の大きさを、耕作で自給するのに必要な人数の面から考えると、技術的な進歩の程度に反比例することがわかる。言い換えると、農耕方法が原始的であればあるほど、生存に必要な収穫物を確保するには、土地を耕す労働力がそれだけ多く必要となる。この段階では集合して共同に生活することが生存にとって本質的な生活様式であり、大きな共同住居はこのような生活様式への解答である。
農耕の方法が改良されるのに伴って、生存するための経済単位は、部族から複合家族あるいは拡大家族へ、さらには、初めは多くの子供、後には少しの子供からなる夫婦家族へと縮小していく。居住者の数の変化に伴い、自然に住居の規模も変化し、広い空間への要求が少なくなる。そして、農耕方法がさらに進歩した段階では、住居は生存のためよりも、快適さを得ることを考えて造られるようになる。ここに至って初めて豊かさの観点から住居の規模と複雑さが考えられるようになるのである。